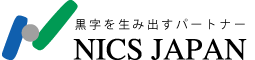⏱️ この記事で分かること(読了時間:約8分)
✅ 営業の積算資料が工事部門で使われない本当の理由
✅ 営業と工事、2つのWBS(工事—工種—種別-細目)の本質的な違い
✅ 多くの建設会社が犯している3つの間違い
✅ 工事部門が構築すべき独自の実行予算体系
✅ MIYABIによる実行予算管理の実現
なぜ営業の積算資料は使われないのか ``` 「営業が作った積算資料、なぜ工事部門で使われないのか?」
多くの建設会社でこの問題が起きています。 そして、多くの会社が間違った解決策を試みています。
「営業と工事でWBS(工事—工種—種別-細目)を統一すればいい」
「共通のフォーマットを作ればいい」
これらは根本的に間違っています。 営業の積算と工事の実行予算は、目的が異なるため、WBS構造も異なって当然なのです。この違いを理解せずに「統一」しようとすることが、問題をさらに複雑にしています。
積算と実行予算は目的が違う
積算と実行予算は、本質的に同じロジックで構成されていますが、その目的は大きく異なります。
【営業の積算】
目的: 受注するための金額を求める
構造:発注者が定義した構造物ベース
視点: 何を作るか
重視する点:過去の実績に基づく迅速な見積作成 営業部門では、積み上げてくるコストの正確性よりも、過去の実績に基づく経験値を予定単価として、より早く見積もりをすることが求められます。
【工事の実行予算】
目的: 安く・漏れなく作業を管理する
構造: 施工計画に基づく作業手順
視点: どうやって作るか
重視する点:予定単価の算出根拠と、より安いコストによる施工 工事部門では、予算(予定)単価の算出根拠に重点が置かれ、施工計画に基づく詳細な単価算定が必要です。
目的が違うので、WBSも違って当然です。
2つのWBS(工事—工種—種別-細目)の構造的な違い
営業のWBSと工事のWBSは、構造そのものが異なります。
営業部門のWBS:構造物ベース
発注者(国交省、県、市町村等)が定義した「何を作るか」の視点で構成されます。
例:
工事
└ 土工
└ 掘削工
└ 普通土掘削
└ バックホウ掘削
工事部門のWBS:施工手順ベース
施工計画に基づく「どうやって作るか」の視点で構成されます。
例:
工事
└ 準備工
└ 測量・丁張設置
└ 掘削工
└ 表土除去
└ 本掘削
└ 残土処理
└ 埋戻工
同じ「掘削」でも:
- 営業:「普通土掘削」として1つの単価でまとめる
- 工事:「表土除去」「本掘削」「残土処理」と分けて、それぞれ異なる単価と施工方法を持つ
このため、単純にマッピングすることはできません
多くの建設会社が犯している3つの間違い
営業と工事の違いを理解せず、多くの建設会社が以下の間違いを犯しています。
**間違い1:発注者のWBSをそのまま実行予算に使う**
営業の積算書をそのまま実行予算書として使用する。
なぜダメなのか:
- 施工実態と合わない
- 作業レベルでの管理ができない
- 実績の歩掛かりが収集できない
**間違い2:積算書の単価に掛け率を適用するだけ**
「積算書の単価の80%で計算する」など、根拠のない掛け率を使用する。
なぜダメなのか:
- 施工方法による原価の違いを反映できない
- 赤字リスクを正確に把握できない
- 改善の余地が見えない
**間違い3:「WBSを統一すれば解決する」と考える**
営業と工事で共通のWBSを作ろうとする。
なぜダメなのか:
- 目的が違うものを無理に統一しても、どちらにとっても使いにくい
- 営業は迅速性を失い、工事は管理精度を失う
- 結局、誰も使わないシステムになる
これらは全て、営業と工事の本質的な違いを理解していないことから起こる間違いです。
重要なのは、工事部門がそのWBSを引き継ぎ、施工計画に基づいてWBSを修正し、単価の算定根拠を構築することです。
工事部門がすべきこと
正しいアプローチは、工事部門が独自の実行予算体系を構築することです。
【工事部門が構築すべき実行予算体系】
**1. 施工計画を立てる**
実際の施工方法を検討します:
- 使用機械の選定
- 作業手順の決定
- 工程の組み立て
**2. 施工手順に基づくWBSを構築する**
実際の作業の流れに沿って分解します:
- 準備工、本体工事、後片付け
- 各工程での具体的な作業
- 並行作業と工程間の関係
**3. 実際の作業に基づく単価を算定する**
施工計画に基づいて、予定単価を積み上げます:
- 投入労務費(人工×単価)
- 使用機械費(台数×時間×単価)
- 材料費(数量×単価) 単なる掛け率ではなく、実際の投入資源から計算します。
**4. 独自の実行予算体系を確立する**
実績を蓄積し、精度を向上させます:
- 実績単価の収集
- 歩掛かりの分析
- 次回予算への反映
積算資料は「参考程度」に見る。実行予算は、施工実態に基づいて一から作る。これが正しいアプローチです。
営業と工事の適切な連携
では、営業と工事は完全に分断されるべきなのでしょうか?
そうではありません。それぞれが独自のWBSを持ちながら、適切な情報共有が必要です。
**営業から工事への引き継ぎ:**
- 発注者の設計書・数量計算書
- 契約金額と内訳 - 特記仕様・現場条件
- 受注時の前提条件
**工事から営業へのフィードバック:**
- 実績単価・歩掛かり情報
- 施工上の課題・リスク
- 次回見積もりへの改善提案
重要なのは、WBSを統一することではなく、必要な情報を適切に共有することです。
MIYABIによる実行予算体系の構築
ニックスジャパンの実行予算管理システム「MIYABI」は、積算システムではありません。
工事部門が、自社の施工計画に基づいて独自の実行予算体系を構築することを支援するシステムです。
**施工手順に基づくWBS作成**
発注者のWBSに縛られず、実際の施工手順に基づく独自のWBSを構築できます。
**作業レベルでの単価算定**
細目(最小作業単位)ごとに、労務・機械・材料の投入量と単価を管理します。
**実績との対比による精度向上**
過去の工事の実績単価・歩掛かりをデータベース化し、次の実行予算作成に活用します。
営業の積算に頼らず、工事独自の管理体系を確立します。
【関連記事】
→ 実行予算と工程表の連動方法
→ 勝ち残る積算戦略
→ 工事と営業の連携強化