⏱️ この記事で分かること(読了時間:約7分)
✅ 実行予算を作る本当の目的とは
✅ 会社と現場代理人を結ぶ誓約書としての役割
✅ 権限委譲を実現する重要な仕組み
✅ 進捗管理のベンチマークとしての機能
✅ 実行予算管理の本質と原点
行予算は、何のために作成するのでしょうか。 多くの企業で「最終損益を予測するため」と答えるでしょう。確かにそれも重要な目的の一つです。しかし、それだけでは実行予算の本質を捉えきれていません。
実行予算には、見逃されがちな3つの本質的な意義があります。
実行予算を作る本当の目的
実行予算管理の意義は、以下の3点に集約されます:
1. 会社と現場代理人との誓約書
2. 会社から現場代理人への権限委譲
3. 最終損益予測及び工事進捗確認
この3つを理解することが、実行予算管理の原点です。
意義1:会社と現場代理人との誓約書
実行予算の最も重要な本質であり、原点と言えるのがこの「誓約書」としての役割です。
**コミットメント(誓約)とは:**
それぞれの現場代理人が社長に成り代わり、「自分だったらこの工事は、この金額で施工できる」という約束をすることです。
これは単なる書類ではありません。現場代理人が:
- 施工方法を十分に検討し - コストを詳細に積み上げ
- 実現可能性を確認した上で
会社に対して行う正式な約束です。
**なぜこれが重要なのか:**
この誓約があって初めて、現場代理人は自らの実行予算に責任を持ちます。誰かに作らされた予算ではなく、自分で作った予算だからこそ、達成に向けて全力を尽くすのです。
逆に、工事部門の誰か他の人が作った実行予算では、現場代理人は「自分の予算」として受け止めません。これでは、達成度を評価することもできません。
意義2:会社から現場代理人への権限委譲
コミットメントを行う訳ですから、当然、権限委譲が発生します。
**権限委譲とは:**
権限委譲された範囲の中で責任を有し、現場代理人は実行予算に基づいて経営資源の利用を提案・実行できる、ということです。
具体的には:
- 協力会社の選定(現場代理人が提案、工事部長・会社が承認)
- 施工方法の決定(実行予算作成時に確定)
- 資材の発注(発注伺いを経て、総務・経理が実行)
- 工程の調整(実行予算の範囲内で判断)
現実には、会社のしがらみや承認プロセスがあります。現場代理人は完全に「自由」ではなく、実行予算を根拠として「提案・判断」を行い、会社が最終承認する、という仕組みです。
重要なのは、実行予算という明確な基準があることで、現場代理人の提案に説得力が生まれ、会社も適切な判断ができる、ということです。
**なぜこれが重要なのか:**
重要なのは、実行予算という明確な基準があることで、現場代理人の提案に説得力が生まれ、会社も適切な判断ができる、ということです。
実行予算がなければ:
- ❌ 現場代理人の提案に根拠がない
- ❌ 会社は判断基準がない
- ❌ 場当たり的な発注になる
実行予算があれば:
- ✅ 「この予算でこの協力会社を使う」という提案ができる
- ✅ 会社は予算との整合性を確認して承認できる
- ✅ 計画的な発注管理が可能になる
権限委譲とは、完全な自由を与えることではなく、明確な基準(実行予算)に基づく提案と承認の仕組みを整えることなのです。
意義3:最終損益予測及び工事進捗確認
実行予算は、第一に最終損益に関する目標であり、工事進捗時点におけるベンチマークでなければいけません。
**最終損益予測:**
工事完了時点で、利益がいくら出るのか(または損失がいくら出るのか)を予測します。これは多くの企業が理解している機能です。
**工事進捗のベンチマーク:**
しかし、私が知る限り、実行予算は最終損益予測のみに終わり、工事の進捗とは連動していない場合が多く見受けられます。 工程表をひいている根拠を明確に答えられる現場代理人は、どれほどいるでしょうか。工程管理が、実行予算とは別に管理されているという、首を傾げざるを得ない管理をしている企業も見受けられます。
**本来あるべき姿:**
実行予算は、施工計画に基づいて作成されます。その施工計画から工程表が作られます。
つまり:
施工計画 → 実行予算 → 工程表
この3つは一体です。
工事進捗の各時点で:
- 予算に対して、どれだけ消化したか
- 工程に対して、どれだけ進んだか
- 出来高に対して、原価はどうか
これらを常に対比することで、実行予算が「生きた管理ツール」になります。
実行予算管理の本質論
実行予算及び予算管理の本質論は、上記の3つの考え方です。
1. **誓約書:** 現場代理人の責任とコミットメント
2. **権限委譲:** 自律的な判断と実行の権限
3. **ベンチマーク:** 進捗管理と損益管理の基準
この考え方をベースに、各企業の実態に合わせて管理することが重要でしょう。
**よくある誤解:**
「実行予算を作ったが、工事が始まったら見ない」
「実行予算は最終損益予測にしか使わない」 「実行予算は工事部門の誰かが作る」
これらは全て、実行予算の本質を理解していない状態です。
MIYABIによる実行予算管理
ニックスジャパンの実行予算管理システム「MIYABI」は、実行予算管理の本質論をベースに設計されています。
**誓約書としての機能:**
現場代理人が自ら作成した実行予算を、承認プロセスを経て確定します。誰が作ったか、いつ承認されたかが記録されます。
**権限委譲と承認プロセス:**
MIYABIでは、「発注伺い書」機能により、実行予算作成段階で協力会社の選定と発注計画を明確にします。
発注伺いのプロセス:
1. 現場代理人が実行予算作成時に発注伺いを作成
2. 工事部長・会社が承認
3. 承認後、総務・経理が発注伺い書を基に注文書・請書を発注
この仕組みにより: ]
- 実行予算と発注が連動
- 承認プロセスが明確化
- 総務・経理の業務効率化
- 予算と実際の発注金額の整合性確保
実行予算を基準として、適切な承認プロセスを経た発注管理が実現します。
**ベンチマークとしての活用:**
最終損益予測だけでなく、月次、日次での進捗管理に対応しています。予算・出来高・原価を常に対比し、工事開始から完了まで一貫した管理が可能です。
実行予算管理の本質を理解し、実践するためのシステムです。
【関連記事】
→ 積算と実行予算はなぜ違うのか
→ 実績管理と工事日報の本質
→ 工事責任者の取り組み姿勢
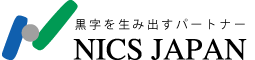
コメントをお書きください