⏱️ この記事で分かること(読了時間:約7分)
✅ 実績管理における工事日報の重要な役割
✅ 工事日報がいい加減に記入される理由
✅ 実績単価と歩掛かりを収集する仕組み
✅ 実行予算との連動が必要な理由
✅ WBS(実行予算体系)構造の一貫性が生む価値
実行予算を作成し、工事が開始されると、いよいよ実績管理の局面に入ります。
実績管理とは、出来高及び原価を把握し、計画(実行予算)に対して工事進捗率並びに損益を把握することです。この段階で、重要な役割を演じるのが工事日報です。
しかし、多くの現場でこの工事日報が、いい加減に記入されています。
実行予算を作成し、工事が開始されると、いよいよ実績管理の局面に入ります。
実績管理とは、出来高及び原価を把握し、計画(実行予算)に対して工事進捗率並びに損益を把握することです。この段階で、重要な役割を演じるのが工事日報です。
しかし、多くの現場でこの工事日報が、いい加減に記入されています。
工事日報の作成が疎かになる理由
実績単価と歩掛かりを収集するためには、実行予算の細別項目と実際に行った作業を連動させなければなりません。
言い換えるならば、歩掛かりを収集できるような実行予算の構成になっているか、ということです。
**実行予算のWBS(実行予算体系)構造:**
工事 → 工種 → 種別 → 細目 この「細目」レベルが、工事日報で記録する作業単位と一致している必要があります。
例えば:
- 実行予算の細目:「掘削工(バックホウ0.7m³)」
- 工事日報の記録:「掘削作業、バックホウ0.7m³、8時間」
この連動があって初めて、実績単価と歩掛かりが正確に収集できます。
積算から実績管理へ、WBS構造の一貫性
積算から実行予算、そして実績管理へと、WBS構造を一貫させて初めて、有用なデータ収集が可能となります。
前回の記事で説明したように、営業の積算WBSと工事の実行予算WBSは異なります。しかし、工事部門内では、以下の一貫性が必要です:
**実行予算のWBS** ↔ **工事日報の作業区分**
この一貫性がないと:
- ❌ 実績データがバラバラになる
- ❌ 歩掛かりが収集できない
- ❌ 実績単価が正確に把握できない
- ❌ 次の工事に活かせない
逆に、WBS構造が一貫していれば:
- ✅ 実績データが体系的に蓄積される
- ✅ 歩掛かりが作業ごとに収集できる
- ✅ 実績単価が正確に把握できる
- ✅ 次の実行予算作成に活用できる
実績単価と歩掛かりとは
実績単価と歩掛かりを感覚的に分かっていても、論理的に捉えている人が少ないようです。
**実績単価とは:**
細目の作業ごとにおける実績原価の単位単価 例:切土法面整形工において、㎡あたり100円
**歩掛かりとは:**
1施工単位当たりの投入資源工数
例:実際の投入機械(0.7m³級バックホウ)によって、㎡あたり0.2時間・台
一般的に建設機械においては、時間当たりの作業能力から計算されることが多いです。
実績単価と歩掛かりの重要性
これらの単価及び歩掛かりの重要性は認識していても、特に歩掛かりについては、実際に作業完了後あるいは工事完了後に分析している企業あるいは個人は少ないようです。
この原因は:
1. 実行予算におけるWBSの構築が曖昧
2. 工事日報の記入が不正確
3. 両者の連動ができていない
実績単価は、将来の見積もり及び実行予算にとって重要な資料となりますので、意識している企業は多いようです。
しかし、歩掛かりについては軽視されがちです。
歩掛かりは:
- 実績単価構成の重要な要素
- 生産性の指標として欠かせないもの
- **コストダウンの可能性を見つける鍵**
KUROJIKAによる実績管理の効率化
ニックスジャパンの工事日報・原価管理システム「KUROJIKA」では、工事日報の作成と実績データの収集を効率化します。
工事日報の作成:
出面帳から投入工数を入力し、工事日報を作成します。タッチパネル式作業予定表システム「e-番割」と組み合わせれば、工数入力も自動化できます。
実績データの自動集計: 日々の工数から、細目(作業)レベルで実績工数を自動集計し、実績原価を算出します。
実行予算のWBS構造と工事日報の作業区分を連動させることで、有用なデータを効率的に収集できます。
【関連記事】
→ 積算と実行予算はなぜ違うのか
→ 実行予算作成の3つの意義
→ 実績単価と歩掛りの重要性(次回)
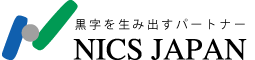
コメントをお書きください